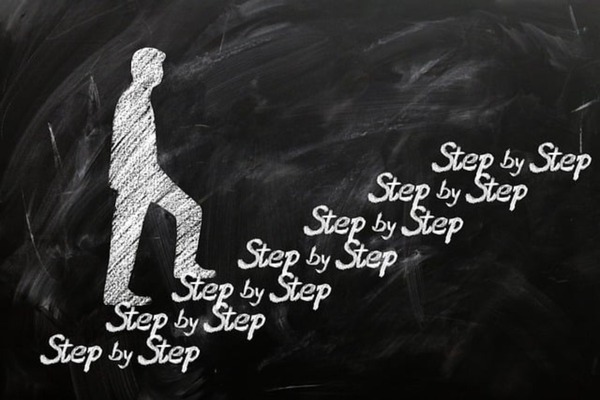退職金にかかる税金はどれくらい?税額の計算方法から注意点まで解説!
会社を辞める際に受け取る「退職金」には、税金が発生します。具体的にはどのくらいの金額を納める必要があるのでしょうか。本記事では、退職金に関する税金の種類、税額の計算方法、そして注意すべきポイントを詳しく解説します。退職金を受け取る際の税務の基礎知識を身につけて、スムーズな退職プランを立てましょう。
目次
退職金にかかる税金とは
個人が給与やボーナスを受け取る場合、課税された税金を納めなければなりません。退職金が支払われる際も、課税対象になります。
ここでは、退職金の意味を簡単に解説した上で、個人が退職金を受け取る際にかかる税金の種類と特徴、課される税額をそれぞれ説明します。
退職金とは
退職金は、定年を迎えた従業員が、務めた会社を辞める際に受け取るお金のことです。勤続年数や従業員の役職、基本給、退職理由などあらゆる項目をベースに算出され、退職慰労金や退職手当と呼ばれることもあります。
従業員が、定年後の生活を安心して過ごすために必要なお金です。ただ、定年を迎えていなくても、会社を辞めるまでの期間で退職金が支払われる場合もあります。
退職金にかかる税金
退職金を受け取る際は、所得税・復興特別所得税・住民税という3種類の税金が発生するため、適切な処理と申告・納税が必要です。以下、それぞれどのような税金なのか、特徴を解説します。
- 所得税
- 復興特別所得税
- 住民税
所得税
所得税は、個人が受け取る所得に対して発生する税金です。退職金だけでなく、給与を受け取ったときや、ボーナスを受け取ったときにもかかるので、所得税は多くの人たちの身近な税金の1つに挙げられます。
税率は5〜45%とされ、受け取る金額が高ければ高いほど、税額が上がる「累進課税」という仕組みが適用されているのが特徴です。会社員の場合は、会社側が源泉徴収します。
復興特別所得税
復興特別所得税は、2013年1月1日から2037年12月31日までの期間で発生する税金です。2011年3月11日に起きた、東日本大震災の復興支援のための財源確保を目的に創設されました。
通常の所得税と併せて徴収されるのが特徴で、復興特別所得税の税率は、所得税額の2.1%です。所得税を納める義務がある方全員が、復興特別所得税の対象者となります。
住民税
住民税は、一定以上の所得がある方が、自身の住所がある市町村や都道府県に対して納める税金です。多くの場合、市町村民税と都道府県民税を併せて住民税と呼びます。
住民税の税率は10%で、内訳は、市町村民税が6%、都道府県民税が4%とされています。退職金に課税される住民税は会社側が算出し、所得税と一緒に源泉徴収されるのが一般的です。
退職金の受け取り方法
退職金は、一時金での受け取りだけでなく、年金形式での受け取りも可能です。場合によっては、2つの形式を併用もできます。
ここでは、対象金の受け取り方法の概要を、メリットやデメリットに触れながら解説します。以下を参考に、自身に合った受け取り方法を選択してみてください。
- 退職一時金
- 退職年金
- 退職一時金と退職年金の併用
退職一時金
退職金は、会社を辞める際に一括で受け取れます。この受け取り方法が、退職一時金です。多くの現金を獲得できる点や、社会保険料がかからない点、控除額が大きくなる点がメリットに挙げられます。
一方、受け取ったお金を使い込んでしまうリスクがある点には、留意が必要です。勤続年数が少ない場合は、控除額が減少します。
退職年金
退職金は、年金形式でも受け取れます。分割でお金が支払われるため、個人が使い込むリスクを避けられるため、老後生活が苦しくなる心配がありません。ただ、退職年金は控除額が少ない点や、物価上昇でお金の価値が下落してしまうリスクがある点には、留意が必要です。
社会保険料の対象になるため、国民年金や健康保険料を支払わなければなりません。
退職一時金と退職年金の併用
退職金における2種類の受け取り方を紹介しましたが、一時金と年金の両方を組み合わせられます。一時金で受け取った部分は、退職所得控除の対象になり、年金で受け取った部分は公的年金等控除を適用できる点がメリットです。
ただし、会社によっては併用形式に対応していないケースもあるので、可否を事前に確認しておくことをおすすめします。
退職金にかかる税金の計算方法
ここでは、退職金にかかる所得税・福特別所得税・住民税の税額計算方法を解説します。まずは退職所得の控除額を計算し、金額に応じた税率のもとで課税される所得額を求めなければなりません。その上で、復興特別所得税と住民税の税率をそれぞれ乗じることで、具体的な税額を算出できます。
税額計算で不安な場合は、税務の知識を持った専門家に相談するのも良いでしょう。
- 退職所得控除額の計算
- 復興特別所得税の計算
- 住民税の計算
退職所得控除額の計算
退職所得控除額は、勤続年数によって計算式が異なるため、本人の勤務状況に併せて計算しなければなりません。勤続年数別の退職所得控除額の計算方法は、以下の通りです。
勤続年数が20年以下 | 実際の勤続年数×40万円 |
|---|---|
勤続年数が21年以上 | 20年×40万円 21年目から退職までの勤続年数×70万円 |
上記の通り、勤続年数が長いほど控除額が大きくなります。ただ、全員が年度区切りで退職するとは限りません。
では、18年8カ月で退職した場合はどのように計算すべきなのでしょうか。この場合、繰り上げて扱う決まりがあるため、勤続年数は19年として計算します。
復興特別所得税の計算
復興特別所得税の税率は前述の通り、所得税額の2.1%です。まず所得税を計算し、算出された金額に対して0.021%を乗じることで、復興特別所得税を導きます。
所得税の税率は5〜45%で、受け取る所得金額によって異なる点に注意しておいてください。所得額と税率・控除額を以下にまとめます。
課税所得額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
1,000円から194万9,000円まで | 5% | 0円 |
195万円から329万9,000円まで | 10% | 9万7,500円 |
330万円から694万9,000円まで | 20% | 42万7,500円 |
695万円から899万9,000円まで | 23% | 63万6,000円 |
900万円から1799万9,000円まで | 33% | 153万6,000円 |
1,800万円から3,900万9,000円まで | 40% | 279万6,000円 |
4,000万円以上 | 45% | 479万6,000円 |
住民税の計算
住民税は、市町村民税6%と都道府県民税4%の合計10%を課税所得に乗じます。住民税率は所得によって変化しません。住民税の計算も復興特別所得税と同様、最初に所得税を求める必要があります。
退職金にかかる税金の税額計算例
ここでは、退職金にかかる所得税の税額計算例を2つ紹介します。
計算例①
1つ目の例として、勤続年数が26年6カ月で、退職金の額が2,000万円のケースを説明します。最初に行うのは、控除額の計算です。
勤続年数が20年を超えているため、以下のような計算式で算出します。勤続年数は繰り上げるため、27年になる点に注意してください。
- 退職所得税の控除額=800万円+70万円×(27年-20年)=1,290万円
上記より、控除額は1,290万円であることがわかりました。次に、課税対象の所得税額を求めます。
- 退職課税所得額=2,000万円-1,290万円×1/2=355万円
これにより、課税される所得金額が355万円と判明しました。先ほど紹介した表から、この場合の税率である20%を乗じ、控除額をマイナスすることで、所得税額を算出できます。
- 所得税額=355万円×20%-42万7,500円=28万2,500円
以上、この場合の所得税額は28万2,500円であることがわかりました。
計算例②
2つ目は、勤続年数が32年8カ月で2,900万円の退職金を受け取った場合の所得税額計算です。この場合も勤続年数が繰り上がり、33年として扱います。
- 退職所得税の控除額=800万円+70万円×(32年-20年)=1,640万円
控除額は1,640万円であることがわかりました。では次に、課税対象の所得税額を求めます。
- 退職課税所得額=2,900万円-1,640万円×1/2=630万円
課税される所得金額が630万円であることがわかりました。この場合の税率である20%を乗じ、さらに控除額をマイナスして所得税額を算出します。
- 所得税額=630万円×20%-42万7,500円=83万2,500円
以上から、この場合の所得税額が83万2,500円であることがわかりました。
退職金の確定申告は必要?
個人に一定額の収入があった場合は、確定申告しなければなりませんが、退職金を受け取った場合も申告の必要があるのでしょうか。ここでは、退職金と確定申告の関係性を解説します。
確定申告は原則不要
結論からいうと、退職金を受け取った場合は、確定申告する必要がありません。多くの場合、会社側が所得税や復興特別所得税、住民税の源泉徴収を行うためです。ただし、この場合は、受け取る本人が会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなければなりません。
確定申告をしたほうが良いケースとは
基本的に、退職金を受け取った際は確定申告する必要はありません。しかし、状況によっては確定申告したほうが良いケースもあります。
自身が以下のケースに当てはまる場合は、確定申告で税金が還付されるかもしれません。
- 退職所得の受給に関する申告書が未提出
- 年内に途中退職し、年末調整が行われていない
- 転職先で年末調整を行ったが、前職の源泉徴収票が未提出
退職金にかかる税金の計算の注意点
ここでは、退職金にかかる税金計算で注意したいポイントを2つ解説します。特に退職所得の受給に関する申告書は、忘れずに会社に提出してください。
- 退職金を受け取った翌年の税金について
- 「退職所得の受給に関する申告書」について
退職金を受け取った翌年の税金について
退職金を受け取ると、翌年に支払う税金が増えるのではと心配されることがありますが、所得税と復興特別所得税は、源泉徴収が行われており、収入としては形状されません。そのため、原則翌年に負担が持ち越されることはありません。
ただ、住民税では退職金を受け取った年の給与所得が多いほど、翌年の課税額が上がるので、注意してください。
「退職所得の受給に関する申告書」について
退職金を受け取った方は、退職所得の受給に関する申告書を会社に提出していない場合、退職所得控除が受けられず、多額の所得税を収めなければなりません。未提出でも、その後確定申告を済ませることで還付を受けられますが、最初に提出したほうがメリットは多いでしょう。
M&Aの対価として退職金を払うときの相談先は経験と知識が豊富なM&A仲介会社がおすすめ
退職金の支払いは、従業員の退職時だけでなく、株式譲渡などのM&Aを実施する際、対価の一部として活用するケースもあります。その際は、多くの専門知識が求められるため、M&A仲介会社に相談することが理想的です。
ここでは、仲介会社の選ぶためのポイントを4つ解説します。
- 相談先の選び方①:M&Aの知識と経験が豊富かどうか
- 相談先の選び方②:自分の会社の業種に精通しているか
- 相談先の選び方③:担当者との相性
- 相談先の選び方④:成功報酬や手数料が明確か
M&Aの知識と経験が豊富かどうか
相談前に、まずはM&Aの知識と経験が豊富にあるかを確認することをおすすめします。実績が多ければ多いほど信頼性が高く、有益な助言が得られるためです。気になる仲介会社があれば、ウェブサイトや問い合わせなどの手段で、過去のサポート実績を把握してください。
自分の会社の業種に精通しているか
自社と同じ業種に強いM&A仲介会社に相談することも大切です。数多くのサポート実績を持つ仲介会社であっても、同業種の事例がなければ、別の仲介会社も視野に入れる必要があります。複数の仲介会社を比較しながら、相談先を絞り込む方法も良いでしょう。
担当者との相性
M&Aの相談や仲介業務は、担当者との相性も重要です。担当者の連絡頻度やレスポンスの速さなど、コミュニケーション面に問題がない仲介会社に相談することをおすすめします。
担当者によって得意分野が異なる場合もあるので、相談時に併せて確認してください。
成功報酬や手数料が明確か
M&A仲介会社にサポートを依頼する場合、相談料や着手金、中間金や成功報酬などの手数料が発生します。予期しない出費を防ぐためにも、料金体系が明確な仲介会社に依頼してみてください。
売却側に着手金や中間金が原則かからない「完全成功報酬型」の仲介会社もおすすめです。
退職金にかかる税金を計算し正しく納めよう
従業員が会社を辞める際に受け取るお金が、退職金です。受け取りには、一時金、年金形式、一時金と年金の併用という3つの方法から選択できます。ただ、通常の給与所得と税額計算方法が異なる点には、注意が必要です。
本記事で紹介した例を参考に、正しい計算方法で納める税額を把握してください。M&Aの対価で退職金の活用を検討されている場合は、一度M&A仲介会社など専門家への相談をおすすめします。
M&A・事業承継のご相談ならM&Aプライムグループ
M&A・事業承継については専門性の高いM&AアドバイザーがいるM&Aプライムグループにご相談ください。
M&Aプライムグループが選ばれる4つの理由
②業界特化の高い専門性
③最短49日、平均7.0ヶ月のスピード成約(2024年9月期実績)
④マッチング専門部署による高いマッチング力
>>M&Aプライムグループの強みの詳細はこちら
M&Aプライムグループは、成約するまで無料の「譲渡企業様完全成功報酬制」のM&A仲介会社です。
無料で相談可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。